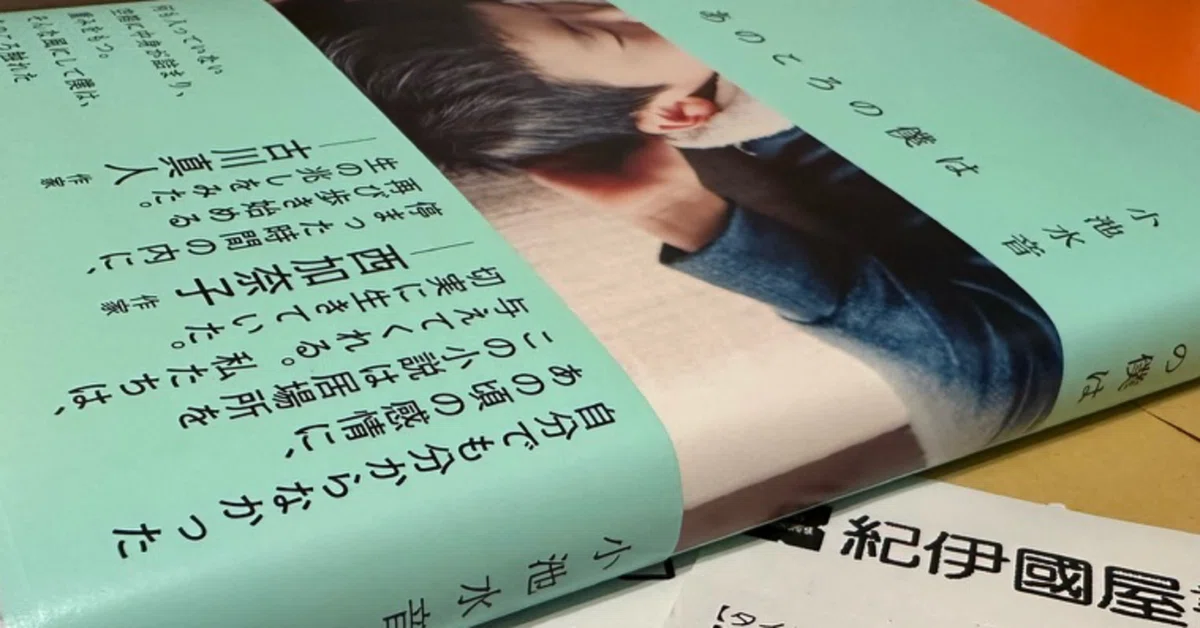小池水音さんの「あの頃の僕は」を読んだ。主人公は五歳の男の子。まだ自分の気持ちを掴めない。僕みたいだ。母を亡くして悲しい、泣きたいという気持ちを理解できずに困っている。それらは気持ちという器に入り切らない。
こぼれ出た自分のマイナスの感情に溺れることは、僕もよくある。それはいつも何が起きたか、その時にはわからない。その時の僕は16歳の今であっても、主人公と同じ気持ちだ。だから僕はこのお話を読んで、作文で賞をもらった直後の自分を感じていた。最近では一番の大波だった。
僕とさりかちゃんはきっと、混乱して現実世界から追放されている。心の中の異次元に迷い込み、先が読めないまま遊んでいる。さりかちゃんは、日本という不慣れなで見知らぬ世界にいきなり放り込まれた。疑問をもつ暇がなかったために、心に傷をおった。だから、中学生になってもそれを言葉にして打ち明けることができず、不登校になるしかなかった。
僕とさりかちゃんは、引っ越しで離れて表面ではつながることができなくなった。けれど異世界ではしっかりと、ずっと繋がっていると考えている。
小説の最後のあたりで、押し入れからゲームを取り出す。幼稚園の頃にやっていたデータで遊び、そのソフトだけをカバンに押し込んで新幹線に乗っている。僕は初恋で経験したことをたくさん引きずり、まだまだ未解決なことが多い。その答を求めて新大阪にいるさりかちゃんに会いに行ったのだ。
青い世界、ゲームと現実世界が一体化したときの瞬間、謎のイギリス風サンドウィッチ。わかっていない事だらけの幼少期に経験したこと。それらは僕とさりかちゃんと、読んでいる私自身の経験がミックスされる体験だ。私自身の幼稚園時代は謎の現象に塗り固められている。
あるはずのないものが見え、動くはずのないものが動き、物事は法則なく起こる。幼稚園生だった頃の怒り、悲しみ、嫌な気持ちの、伝えられなかったそれらを、「あの頃の僕は」が全部言ってくれたような気がした。そしてその感情は文章を読んでいるというより、とても重いデータ、4Kの映像が迫ってくるような体験だった。